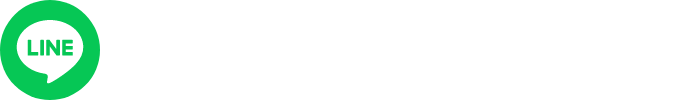松岡 麻依子 氏
- JICA海外協力隊 マダガスカル隊員
- コミュニティ開発
- 松岡 麻依子 氏
- 2009年 外国語学部 英米語学科 卒業

大学生時代から抱いていた海外ボランティアへの憧れ
現在、JICA海外協力隊としてマダガスカルでボランティア活動をしています。目標はワークショップや情報提供を通して、地方に住む農民の暮らしを豊かにすること。活動中は、コミュニケーションの一環として日本文化を紹介することもよくあります。 海外ボランティアや国際協力といった分野には、関西外大在学中から興味を持っていました。4回生のとき、学内掲示板に貼られた青年海外協力隊の募集ポスターを偶然目にしたのです。協力隊に憧れていた私は、迷うことなく応募しました。しかし、そう簡単に合格できるものでもなく、結果は書類選考落ち。今考えると、当時はボランティアとして何がしたいのか、何ができるのかという志が曖昧だったため、通らなかったのだろうと思います。ただ、私の熱意は少しも冷めず、「社会人として経験を積み、開発途上国のために役に立てる人間になってからもう一度応募しよう」と決意を新たにしたことを覚えています。

イタリアでの留学生活
在学中に最も印象に残っているのは、約10ヵ月間のイタリア留学への挑戦です。とにかく「イタリア語を早く習得したい!」という気持ちが強かった私。できるだけ日本語を使わないよう、一緒に留学した関西外大の仲間とも日本語を使わずイタリア語で会話するように心がけていました。その光景が不思議だったようで、私たちの会話を聞いた現地の学生から「なぜ日本人同士なのにイタリア語で話すの?」と質問されることも多かったです。「ここはイタリアなんだから、イタリア語を話すのは普通でしょ?」そう私が答えると、嬉しそうにしてくれたことは今でも鮮明に覚えています。私たちがイタリア語で話していたから、彼らも話しかけやすかったのだと後に明かしてくれました。
色々なプログラムを経験しましたが、調理実習が一番思い出深いですね。リゾットやミラノ風カツレツ、ジェノベーゼソースなど、作ったのはいずれもイタリア料理の定番ばかり。レシピは頭の中に入っているので、今でも時々作ることがあります。そのたびに当時を思い出し、充実した時間を過ごせていたのだなと噛みしめることもしばしば。今となっては楽しい思い出ですが、実は最初、大学からは調理実習を単位互換することは難しいと言われていました。この授業が好きだった私は、単位として認めてもらうため、大学に直談判。イタリア文化を理解するために料理や食事の面からアプローチすることの重要性を一生懸命説明しました。そんな私の熱意を認めてくださり、無事に了承を得ることができました。調理実習の思い出が深く残っているのは、この経験があったからかもしれません。
色々なプログラムを経験しましたが、調理実習が一番思い出深いですね。リゾットやミラノ風カツレツ、ジェノベーゼソースなど、作ったのはいずれもイタリア料理の定番ばかり。レシピは頭の中に入っているので、今でも時々作ることがあります。そのたびに当時を思い出し、充実した時間を過ごせていたのだなと噛みしめることもしばしば。今となっては楽しい思い出ですが、実は最初、大学からは調理実習を単位互換することは難しいと言われていました。この授業が好きだった私は、単位として認めてもらうため、大学に直談判。イタリア文化を理解するために料理や食事の面からアプローチすることの重要性を一生懸命説明しました。そんな私の熱意を認めてくださり、無事に了承を得ることができました。調理実習の思い出が深く残っているのは、この経験があったからかもしれません。
ディベートサークルでの成長
大学生活を充実したものにしたい。そう考えてたどり着いたのが関西外大のディベートサークルでした。英語力を上げるため、学内での練習はもちろん、他大学との練習会にも積極的に参加しました。活動を通して身についたのは、相手が理解しやすいよう論理的に説明する力。また、他大学との交流や試合でのディベートで向上心が刺激され、英語学習への向き合い方にも変化がありました。わからないところは図書館で調べたり、英字新聞を読む習慣ができたり。そのおかげか、留学審査ではイタリア圏のほかに、英語圏への留学検定にも合格。もともとは語学力を上げるための入部でしたが、それ以外のスキルも伸ばすことができたサークル活動でした。ほかにも、関西の大学のESS(※)を集めた団体で大会運営の手伝いなども経験し、学外の人とも多くかかわりがありましたね。
※Englich Speaking Societyの略で、大学生を中心とした英語学習・交流サークルのこと
※Englich Speaking Societyの略で、大学生を中心とした英語学習・交流サークルのこと
卒業後のキャリア変遷
地元広島のホテルが、私の社会人としてのスタート地点です。平和記念公園や国際会議場の近くにあったため外国人のお客様も多く、関西外大での経験が大いに役に立ちました。その後、心機一転イタリア系の物流輸送会社に転職。事務や出向先での貿易実務、営業職としての海外出張など、さまざまな職種を経験しました。パリコレに出展されるお客様に同行し、パリへと出張したこともあります。
これからもっと外の世界に飛び出していこう!新型コロナウイルスのパンデミックが世界を襲ったのは、ちょうど私がそんな思いを持った時のことでした。行動制限がある生活のなかで思いついたのが、地方への移住。11年勤めた会社を退職し、兵庫県へ引っ越しました。今思えば、ここが私の人生のターニングポイントだったのかもしれません。農業についてもっと詳しく知りたいという以前から持っていた思いを実現すべく、移住後は京都のお茶農家さんや和歌山の梅農家さんの元に住み込みで働きました。沖縄の民宿で働いた時期もあります。いくつかの地方を転々とした後、長年目標にしていたJICA海外協力隊に再びチャレンジ。審査にも無事合格し、学生時代からの夢だった海外ボランティアとして、現在マダガスカルで活動中です。
これからもっと外の世界に飛び出していこう!新型コロナウイルスのパンデミックが世界を襲ったのは、ちょうど私がそんな思いを持った時のことでした。行動制限がある生活のなかで思いついたのが、地方への移住。11年勤めた会社を退職し、兵庫県へ引っ越しました。今思えば、ここが私の人生のターニングポイントだったのかもしれません。農業についてもっと詳しく知りたいという以前から持っていた思いを実現すべく、移住後は京都のお茶農家さんや和歌山の梅農家さんの元に住み込みで働きました。沖縄の民宿で働いた時期もあります。いくつかの地方を転々とした後、長年目標にしていたJICA海外協力隊に再びチャレンジ。審査にも無事合格し、学生時代からの夢だった海外ボランティアとして、現在マダガスカルで活動中です。

ボランティアとして大切にしていること
現地の人々の生活を観察し、できるだけ同じ暮らしをすることを意識しています。買い物のときは周りの人と同じものを買ったり、かまどを使って料理してみたり。いいなと思ったことは、何事も実践してみるようにしています。ただ、そこで悩みの種になるのが言葉の壁です。公用語はマダガスカル語とフランス語。派遣される前に語学の訓練もあったのですが、それでも生活するのに十分とは言えないレベルでした。実際の活動が始まってからも、毎日ノートとペンを持ち歩き、人に聞いてはメモを取って覚える、を繰り返す日々。この習慣は語学力の向上だけでなく、地域の人とのコミュニケーションにもなるので、着任から一年経った今でも続けています。


現地であったうれしい出来事
マダガスカルでは今、薪の大量消費による森林減少が深刻な問題となっています。現地での料理には、薪を使ったかまどの熱が必要不可欠だからです。そこで私が思いついたのが「かまどづくり」のワークショップ。薪を効率的に使用できるかまどを皆が作ることができれば、薪の使用量を減らして森林減少を防ぐだけでなく、燃料代の節約にもつながり一石二鳥だと考えたのです。後日、ほとんどの参加者が実際にご自身の家でかまどを作ったこと、そしてそれが本当に薪の節約につながっていることを教えてくれました。現地住民の生活改善につながるとともに環境問題解決の一助にもなれたことがとてもうれしかったです。
JICA海外協力隊としての任期はあと1年。着任したばかりの頃は、飛び込みでワークショップの開催を提案しなければ何もできない状況でしたが、最近では「人を集めるからワークショップをやってほしい」と声をかけられることも増えました。見え始めた成果を糧に、コミュニケーションを通して現地住民のために尽力したいと思っています。
JICA海外協力隊としての任期はあと1年。着任したばかりの頃は、飛び込みでワークショップの開催を提案しなければ何もできない状況でしたが、最近では「人を集めるからワークショップをやってほしい」と声をかけられることも増えました。見え始めた成果を糧に、コミュニケーションを通して現地住民のために尽力したいと思っています。

大学生の皆さんへ
私は関西外大を卒業してからさまざまな仕事をしてきました。今はボランティアとして働いていますが、将来に不安はまったくありません。なぜなら、これまでの大学生活や留学、そして社会で出会った方々とのご縁と、仕事やボランティア活動で培った経験が常に私を支えてくれるからです。ディベートサークルで培った「相手にわかりやすいよう、順序立てて説明する力」は、物流会社の勤務時代に存分に発揮できました。そんな物流会社での営業経験も、マダガスカルでワークショップの飛び込み営業をする際に活きています。
ボランティア任期満了後の身の振り方はまだ決まっていませんが、日本の農業と国際協力に関わる仕事がしたいと思っています。私が進路を選ぶときの判断基準は、どちらの方がワクワクするか。私自身のワクワクを探しながら、これから社会人になる関西外大生の皆さんがどのような選択をして、何に挑戦していくのかも見守りたいです。関西外大には国内、海外の両方に多くの同窓会支部があります。どこかの同窓会で出会えた際は、ぜひ皆さんのワクワクすることを教えてください。
ボランティア任期満了後の身の振り方はまだ決まっていませんが、日本の農業と国際協力に関わる仕事がしたいと思っています。私が進路を選ぶときの判断基準は、どちらの方がワクワクするか。私自身のワクワクを探しながら、これから社会人になる関西外大生の皆さんがどのような選択をして、何に挑戦していくのかも見守りたいです。関西外大には国内、海外の両方に多くの同窓会支部があります。どこかの同窓会で出会えた際は、ぜひ皆さんのワクワクすることを教えてください。